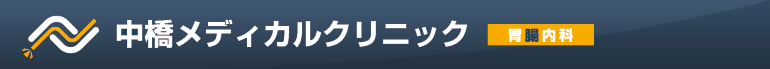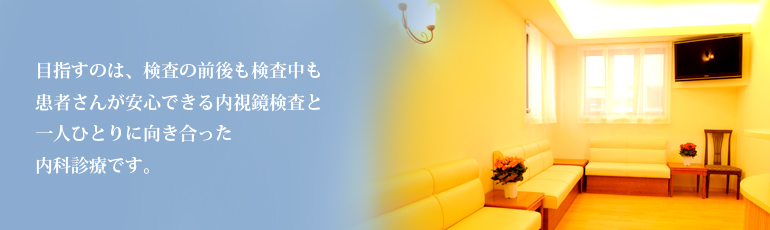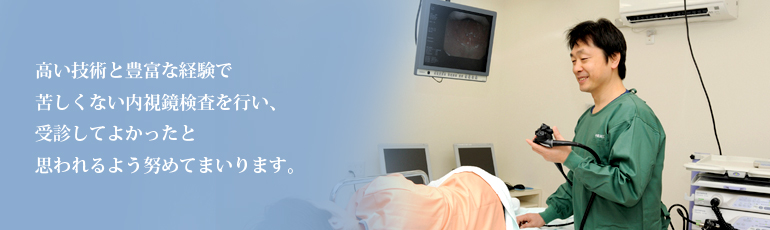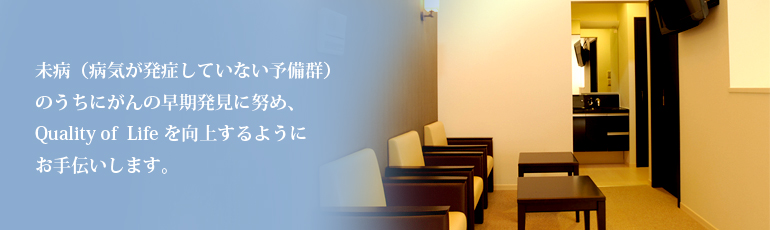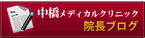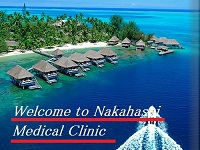ヘリコバクター・ピロリ菌とは
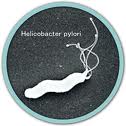 大きさは2.5~5μmで肉眼では見えません |
|
保険で治療を受けるには
|
胃バリウムで「要精査」となった場合
|
ABC健診で要精査になった方
|
ヘリコバクター・ピロリ菌検査方法
検査方法は5通りあります胃カメラでピロリ菌感染胃炎を観察診断することが基本です。 以下はその補助診断方法です。
<胃カメラを用いない方法> 胃炎には「ピロリ菌感染胃炎」とそれ以外の「胃炎」があり、内視鏡診断を行うことが最も確実な方法で以上はその補助診断となります。 上記検査はあくまで目安であり内視鏡観察医の眼力が重要と考えます。 日本ヘリコバクター学会認定医の院長が診療にあたります。 |
ピロリ菌感染胃炎の保険治療
【保険内治療の対象となる方】
【保険内治療の対象とならない方】
【除菌治療の流れ】
|
自費診療の料金(保険での検査や治療を希望されない場合)
| ピロリ菌がいなかった方(検査のみで終わる方) | |
|---|---|
|
I. 尿検査(所要時間20分)(通院;1回)注1) (→ピロリ菌の情報が全くなくはじめてピロリ菌のチェックを受ける方に向いた簡易的な検査法です) |
4,000円 |
|
Ⅱ. 尿素呼気テスト+診察料(感度95%以上)(通院;2回)注2) (→以前除菌治療を受けたが、成功の有無を確認していない方に向いた検査です) |
11,500円 |
| 除菌料 | |
|
Ⅲ.検診などでピロリ菌感染が明らかな場合 注2) 除菌治療(処方費用)+尿素呼気検査による確認(6週間後) |
14,500円 |
|
尿素呼気試験には8時間の絶食が必要です | |
*注1)ピロリ菌外来は16:30までの受付となります。
*注2)血清ピロリ菌抗体検査、尿素呼気テストの結果には1週間を要します
*注2)血清ピロリ菌抗体検査、尿素呼気テストの結果には1週間を要します
ヘリコバクター・ピロリ菌の有無と萎縮性胃炎の程度であなたの胃がん危険度がわかります
下記の表はヘリコバクター(以下HP)の存在(+かー)とペプシノーゲン(以下PG)の存在(+かー)をみた場合の胃がんの発生数をあらわした表です。
| 発見胃癌数 | オッズ比 | 推奨検診間隔 | |
|---|---|---|---|
| A群 HP(-)PG法(-) | 0/966 | ×1 | 3~5年間隔 |
| B群 HP(+)PG法(-) | 25/2327 | ×9.8 | 1年間隔 |
| C群 HP(+)PG法(+) | 30/1329 | ×19.6 | 1年間隔 |
| D群 HP(-)PG法(+) | 4/33 | ×120.4 | 半年~1年間隔 |
表の説明
ペプシンの前駆体であるペプシノーゲンIとIIを測定しその強弱で胃粘膜の萎縮の程度を数値化したものがPG法です。PG法陽性が即胃がんであるという意味ではありません。腸上皮化生を伴う萎縮性胃炎では高率に胃がんが発見されているので萎縮の程度を数値化して検診に役立てようと試みられているのがPG法です。PG法陽性とは萎縮性胃炎が進んでいることを表現しておりPG法陰性とは萎縮の少ない胃であることを表現しています。萎縮性胃炎は慢性胃炎が進行した状態と言え、長年ヘリコバクター・ピロリ菌の感染が継続していた胃のことです。
A群での胃がん発生数を1とした場合それぞれの群での実際に発生した胃がん発生のリスクを表示しています。これまでヘリコバクターに感染した既往がなく、胃粘膜の萎縮性変化もない胃では胃がんは発生していないことがわかります。このような胃をお持ちの方の検診間隔は3~5年でよいと思われます。一方、ヘリコバクターの存在が確認できた例あるいは萎縮性胃炎と言われた例では毎年検診を受ける必要があると考えています。
注意)除菌によってB群およびC群がD群になるわけではありません。まず、ピロリ菌は強い酸を産生する胃粘膜でしか生きることができません。萎縮が進み酸が弱くなった胃ではピロリ菌の住環境が悪くなり自ら消滅してしまうことによってD群に至ります。逆に除菌によってピロリ菌が消失した胃では萎縮性胃炎の進行が止まります。興味ある報告では、早期胃がん内視鏡治療症例を対象に除菌した群と除菌しなかった群を比べた場合、除菌しなかった群では1/8の確率で異所性異時性再発(時を別にして治療した場所以外で胃がんが発生すること)があると言われ、除菌した群では異時性再発はなかったと報告されています。たとえ萎縮が進んだ胃であっても除菌することにより胃がんの発生を抑えていることがわかっています。
ペプシンの前駆体であるペプシノーゲンIとIIを測定しその強弱で胃粘膜の萎縮の程度を数値化したものがPG法です。PG法陽性が即胃がんであるという意味ではありません。腸上皮化生を伴う萎縮性胃炎では高率に胃がんが発見されているので萎縮の程度を数値化して検診に役立てようと試みられているのがPG法です。PG法陽性とは萎縮性胃炎が進んでいることを表現しておりPG法陰性とは萎縮の少ない胃であることを表現しています。萎縮性胃炎は慢性胃炎が進行した状態と言え、長年ヘリコバクター・ピロリ菌の感染が継続していた胃のことです。
A群での胃がん発生数を1とした場合それぞれの群での実際に発生した胃がん発生のリスクを表示しています。これまでヘリコバクターに感染した既往がなく、胃粘膜の萎縮性変化もない胃では胃がんは発生していないことがわかります。このような胃をお持ちの方の検診間隔は3~5年でよいと思われます。一方、ヘリコバクターの存在が確認できた例あるいは萎縮性胃炎と言われた例では毎年検診を受ける必要があると考えています。
(日本がん検診学会誌より一部改定)
注意)除菌によってB群およびC群がD群になるわけではありません。まず、ピロリ菌は強い酸を産生する胃粘膜でしか生きることができません。萎縮が進み酸が弱くなった胃ではピロリ菌の住環境が悪くなり自ら消滅してしまうことによってD群に至ります。逆に除菌によってピロリ菌が消失した胃では萎縮性胃炎の進行が止まります。興味ある報告では、早期胃がん内視鏡治療症例を対象に除菌した群と除菌しなかった群を比べた場合、除菌しなかった群では1/8の確率で異所性異時性再発(時を別にして治療した場所以外で胃がんが発生すること)があると言われ、除菌した群では異時性再発はなかったと報告されています。たとえ萎縮が進んだ胃であっても除菌することにより胃がんの発生を抑えていることがわかっています。